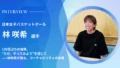組織経営において、人事制度はあたかも当然のように存在してきました。等級制度、評価制度、報酬制度──多くの企業で何らかの人事制度が整備され、日々運用されています。制度の設計や見直しは、多くの経営者や人事部門にとって継続的なテーマになっています。
しかし、少し立ち止まって考えてみると、「人事制度は本当に必要なのか?」という問い自体が、十分に検討されることはあまりありません。制度疲労、制度への不信感、制度の形骸化が語られる一方で、「制度はあって当たり前」という前提がそのまま残り続けているケースも多いのが実情です。
そこで本記事では、「人事制度は本当に必要なのか?」という問いをあらためて正面から考えてみます。伝統的な所謂人事制度はどのような前提を元に設計され、その前提は今どうなっているのか、新たな制度が必要なのか、それとも制度自体がそもそも必要ないのか──。
読者の方が自身の考えを深めていくための材料になれば幸いです。
【関連記事】「人事制度」については、以下の記事もご確認ください。
・人事制度とは?
・等級制度とは?
・評価制度とは?
・報酬制度とは?
人事制度は本当に必要か?
最初に本記事の基本的な立場を明確にしておきますと、それは「現在一般に言われている『等級・評価・報酬』を中心とした所謂人事制度は必ずしも不可欠ではないが、一部の例外的条件を除けば、経営者と従業員双方のニーズの重なりうる領域を見出しやすくすることを通じて組織目標を持続的に達成するための『制度的な枠組』そのものは、何らかの形で依然として必要。」というものです。
ここでいう「制度的な枠組み」とは、単なる仕組の有無ではなく、組織の中で役割・期待・貢献・処遇・成長などの関係性を構造的に整理し、共通理解を生み出す基盤を指しています。
人事制度そのものが不要となりえる一部の例外的条件としては、例えば以下のようなものが挙げられるでしょう。
- ごく少人数の起業初期段階(数名規模)
- 短期限定のプロジェクト組織
- 完全フリーランス型の契約連合
これらは、制度を整備・運用するコストが便益を上回る典型例です。
こうした例外を除けば、制度的な枠組は必要ではないかと考えています。
人事制度の中目的と所謂人事制度のメカニズム
人事制度とは、組織目標を持続的に達成していくために、経営者と従業員双方のニーズが重なりうる領域を見出しやすくする暫定的な枠組みです。その究極的な目標は組織目標の持続的な達成に寄与することですが、中目的としては以下の4つが多くの組織で共通的に発生しうる代表的なものです(人事制度自体についての詳細はこちらを参照ください。)。
- 理想的な人材配置の実現
- 組織の方針の浸透
- 動機付け
- マネジメントの効率向上
これらの中目的を達成するために、等級・評価・報酬を中心とした所謂人事制度では、経営者が従業員に求める期待値とそれに対する従業員の実績値に応じた処遇決定方法を通じて、経営者側のニーズと従業員側のニーズをマッチングさせ、組織・人材マネジメントを行っています。
具体的には、等級制度によってレベル別の期待値を示したうえで従業員を階層にレベル分けし、評価制度によってレベル別に実績値を測り、報酬制度で実績値に応じた処遇(金銭的報酬やレベル分け)を決定するというメカニズムを利用しています。
所謂人事制度を支えてきた暗黙の前提
この所謂人事制度が中目的を果たすために利用しているメカニズムの背景には、いくつかの暗黙の前提が存在します。
現行の所謂人事制度(等級・評価・報酬型)は、次のような前提の元に構築されていると言えるでしょう。
| 観点 | 暗黙の前提 |
|---|---|
| 経営環境 | 比較的安定しており未来は見通せるもの |
| 人材ポリシー | 長期雇用・時間をかけて序列的昇進するのが前提 |
| 動機付け | 外発的動機づけ(主に金銭や地位)が有効 |
| 組織構造 | 階層的統制が基本 |
| 管理方法 | 上位者が管理・評価する |
| 評価するという行為 | 成果・行動は客観的・定量的に測定可能 |
| 制度運用可能性 | マネージャーが制度を適切に運用できる |
これらの前提が現実に適合している限り、制度は比較的安定的に機能します。
しかし、現代ではこの前提が揺らぎ始めています。
前提と現実との乖離が起きる場面
制度の前提が現実に適合しなくなると、様々な制度疲労・矛盾・不全が生じ始めます。
以下に代表的な乖離場面を整理します。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 経営環境 | VUCA |
| 動機付け | 金銭・地位だけでは動かない人材の増加・多様化 |
| キャリア観 | 序列型キャリアに乗らない人材増加 |
| 組織構造 | 多層化による機動力低下 |
| 管理方法 | プレイングマネージャー化による管理不全 |
| 評価対象 | 定量化困難な貢献の重要性増加 |
オルタナティブ型の人事制度の登場
こうした制度疲労等への対応として、伝統的な所謂人事制度に対するオルタナティブ型の人事制度が登場しています。
たとえば:
- No Rating型評価制度
- ティール組織
- 期待ベース人事
- ホラクラシー/セルフマネジメント
- 対話駆動型評価と継続的フィードバック
ただし、これらの試みも人事制度自体が不要という話ではなく、伝統的な所謂人事制度が前提としてきたものを更新し、現実と整合的に再設計しようとするアプローチと言えるでしょう。
つまり「制度自体が不要だ」という議論ではなく、制度の設計思想そのものを問い直す議論が必要というのが本質です。
ティール組織を例に学ぶ、新たな制度的な枠組み
ここでは、前章でもオルタナティブ型の人事制度として挙げたティール組織を例に、どうオルタナティブ型が伝統的な所謂人事制度とは違うアプローチで現実に対応しようとしているのか、その上でそれでも「制度自体が不要」なのではなく「制度的な枠組み」としては依然必要ということを説明します。
ティール組織がいかに伝統的な所謂人事制度と異なるか
ティール組織自体の説明は別記事に譲るとして、ティール組織がいかに伝統的な所謂人事制度と異なるかについてまとめると以下のようになります。
- 等級(ヒエラルキー的な階層構造)の排除
- 評価(上位者からの序列化)の排除
- 報酬の自己決定
- 代わりに ロールベースの柔軟な役割分担 と セルフマネジメント によって運用
つまり、伝統的な所謂人事制度の根幹を成す「序列」「序列に基づく権限」「序列に基づく処遇」をほぼすべて放棄する、極めて異質なアプローチだということです。
ティール組織はどのように人事制度の中目的にアプローチしているか
ティール組織では各中目的の実現について以下のようなアプローチをとっています。
| 中目的 | ティールのアプローチ |
|---|
| 理想的な人材配置の実現 | ロールは固定せず、メンバーの意思と状況に応じて柔軟に引き受け・手放しを繰り返す。配置異動のルールより「適応」を優先する。 |
| 組織の方針の浸透 | 「存在目的(パーパス)」をメンバーで共有し、その目的に合致した意思決定を各ロールが自律的に行う。ピラミッド的上下関係ではなく、共通の目的を軸に整合性を保つ。 |
| 動機付け | 上下関係による報酬差や序列ではなく、自己決定と存在目的への共感による内発的動機づけを重視する。 |
| マネジメントの効率性向上 | 管理職による一元的管理ではなく、メンバー同士の相互フィードバックやアドバイスプロセスを共通ルールとして設け、意思決定の質を保つ。 |
同じ中目的の実現に違うアプローチで挑んでいても、何かしらのルールや経営者のニーズと従業員のニーズの重なりを見出しやすくするための制度的枠組みはティール組織にも存在することがおわかり頂けるかと思います。
まとめ
- 伝統的な所謂人事制度は、それが設計の前提していたものと現実との乖離が大きくなってきている。
- 現実との整合性をより高くするために、伝統的な所謂人事制度とは異なるオルタナティブが登場してきている。
- かといって人事制度自体が不要であるということではなく、いずれにせよ制度的な枠組みは必要である。
- 制度設計における議論は、「必要か否か」ではなく「どのような前提に立って設計するか」 という問いで捉え直す必要がある。
- 組織が置かれている個別具体的な状況を踏まえた上で考えた時に、伝統的な所謂人事制度に近い設計になる場合もあれば、オルタナティブ型に近い設計の制度的枠組みになる場合もある。
こうした議論を自組織固有の事情に即して考えていきたい場合は、是非問い合わせください。