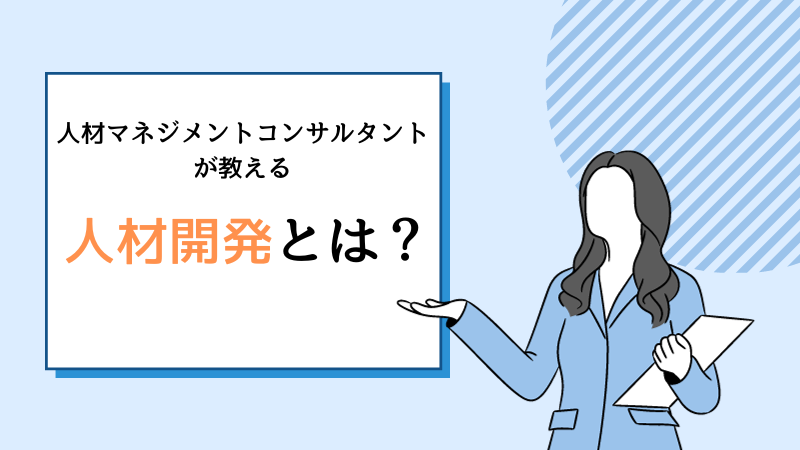人材開発とは研修やOJTを指す言葉ではなく、組織の戦略の実現や目標達成を目的とした学習プロセスや支援を指します。
人材を組織の内部に囲い、長期で雇用することで人材を育成してきた日本型雇用の企業にとって、人材開発は重要な意味を持っていましたが、社会情勢が急激に変化している今、この人材開発が更に注目を集めています。
今回は、そうしたニーズにも応えられるよう、人材開発の正しい知識と目的、具体的な手法や注意点について理論からしっかりと解説します。
人材開発とは
人材開発とは、組織の戦略の実現や目標達成のために、組織のメンバーにとって必要となるような知識、スキル、コンピテンシー、信念を提供し、これらの獲得のために従業員が学習するプロセスを促進・支援することを指します。
この定義からもわかる通り、人材開発は組織の戦略の実現や目標達成を目的とした活動です。
そのため、よく人材開発の説明の中で使われる研修やOJTなどはあくまでも手段であって、それ自体を目的としているわけではありません。人材開発は人間の学習プロセスを手段として用いて、組織や現場にプラスのインパクトをもたらし、従業員へプラスの変化を導くことを目的として行われます。
すなわち、従業員が学びプラスの変化が感じられたことと、経営や現場にプラスのインパクトが生じたことの2つが揃っていて初めて、適切な人材開発がなされていると言えます。
人材育成との違い
人材開発という言葉に近しい言葉として「人材育成」が挙げられます。
これは人材開発とほぼ同義語です。
ただ、人材開発とセットで語られる言葉として「組織開発」があり、人材開発と双璧をなす重要な概念のため、フォスターリンクでは人材開発という表現を採用しています。
組織開発との違い
上述したように、人材開発と切っても切り離せない概念に、「組織開発」というキーワードが挙げられます。
組織開発とは、計画的で組織全体を対象とした、トップによって管理された組織の効果性と健全さの向上のための努力であり、行動科学の知識を用いて組織プロセスに計画的に介入することで実現される活動を指します。
人材開発と同様に、組織開発も経営や現場にプラスのインパクトをもたらすことを目的とした手段の一つと言えます。ただ、人材開発の場面においては個人が働きかけの対象となるのに対して、組織開発においては組織がその対象となります。
例えば、従業員のエンゲージメントが低いという事実に対して、対話を通じて職場の課題を明らかにし、解決へと取り組むことは組織開発となります。一方で、従業員のモチベーション低下が原因であり、マネジメント層の部下へのコーチング教育を施すということになればそれは人材開発の領域となります。
つまり、組織開発は組織の人と人との関係を変えることを手段として用い、組織がしっかりと機能するように働きかけ、企業の戦略実現に寄与するということになります。
【関連記事】組織開発に関しては、こちらの記事もご確認ください。
人材開発の必要性が高まっている背景
日本において人材開発の必要性が企業で高まっている背景としては、政府や経済団体が人事課題を政策における課題として取り上げる傾向が強まったことが挙げられます。
特にここ10年ほどの間に、人材開発の必要性は一気に注目されるようになってきています。
その中でも、特に影響を与えたトピックスとしては「女性活躍推進」の動きや「働き方改革」、「ミドルシニアの活性化」の3つが挙げられます。
2015年頃から政府主導で始まった女性活躍推進の取り組みを契機に、企業の経営課題として、女性管理職比率の向上やいわゆるM字カーブの改善などに向き合うことが求められています。また、ワークライフバランスというキーワードも一般的になり、長時間労働の是正が当たり前に求められる社会になりつつあります。
更に高齢化が進む中、ミドルシニアを活性化することも社会課題となっています。ミドルシニアの活性化には、給与に見合った学び直しをすることで生産性を向上させるなどの取り組みも必要となることでしょう。
このように、これまで研修のような形でオペレーショナルに行っていた人材開発だけでは難しく、現場のOJT形式でも対応が困難な課題が生じてきていることから、より高度な方法を探るべく人材開発の必要性が高まってきていると言えるでしょう。
人材開発の目的
人材開発は、従業員が学ぶことによってプラスの変化が感じられ、かつ経営や現場にプラスのインパクトを生じさせることを目的としていると解説しました。
それでは、具体的にそのプラスの変化やインパクトとは何を指しているのでしょうか。
ここでは、その変化やインパクトが現れる3つの視点について深掘りしながら、人材開発の目的について考察していきます。
①人的資源に関わる数値
一般的に、人的資源とは組織やビジネスにおいてその活動や運営をサポートするための人々を指します。
人的資源に関わる数値とは、例えば離職率や定着率、エンゲージメントの数値などがあります。これらは間接的に生産性につながっていきます。例えば、離職率が高い場合、人材不足をカバーするために採用や教育を繰り返すことによって、業務の生産性の低下につながります。
人材開発が適切に機能している場合、この数値を向上させることにつながります。
②職場の健全性や効果性を現す数値
職場の健全性や効果性を現す数値とは、職場ごとに集計されたエンゲージメントの数値やストレスチェックなどの職場の状態が現れるものを指します。これが健全であるということは、職場の中で目標を共有できており、メンバー同士のコミュニケーションや役割分担が適切になされていると言えます。また、効果性とは、組織全体が目標達成に向けて動いており共に研鑽し合えている状態を指し、人材開発が正しく行われた場合こうした数値を高めることにつながります。
③経営指標
経営指標とは、端的に言うと売上や利益を指します。
これは人材開発が直接的に売上や利益を上げるという意味ではありません。あくまでも人材開発を行うことによって、会社や組織のメンバーやマネジメント層に行動変容が起き、それらを戦略と連動させることを通して、間接的に売上や利益を向上させることにつながると言えます。
以上をまとめると、人材開発の目的は、人的資源に関わる数値と職場の健全性・効果性を現す数値を高め、従業員へ行動変容を起こすことによって間接的に経営指標を高めていくことと言えるでしょう。
人材開発における手法
個人に対して働きかける人材開発は、人材の課題や組織の課題が何かによって、対象者やその開発方法も多種多様になります。
そのため、ここではその目的に着目して、大きく2つの人材開発の分類とその具体的な手法について解説していきます。
(1)キャリアステージに応じた人材開発
初めに、従業員の職位やポジション、年齢などに応じたその発達ステージに応じて行われる人材開発について説明します。
具体的には以下のような取り組みがあります。
①新人研修
新卒一括採用という日本型雇用を支える代表的な研修の一つが新人研修です。
人材開発に関する代表的な概念の中に「組織社会化」という概念があります。これは、組織の目標達成に向けて新しくその組織に加わったメンバーに対して、必要な知識や信念、態度などを獲得できるようにし、その組織の一員にすることを指します。
新人研修はまさにこの組織社会化を実現するための手段です。
日本の教育機関では企業の即戦力としてすぐに働けるような職業訓練を行なっていないため、新人研修ではそのギャップを埋めるためのカリキュラムを中心に行います。例えば、その職場で必要となる最低限の知識やスキル、マナーなどを教え、その上で配属先での就業につなげるというようなステップを設けます。新人研修の期間は企業や組織によって様々ですが、一般的には数週間から3ヶ月程度で行います。また、近年では若手社員の早期離職が増えている観点から、この新人研修期間を延ばす期間を増やす企業も出てきています。
②次世代リーダーシップ開発研修
最近では将来の経営幹部育成を目的として、次世代リーダーシップ開発研修を実施する企業も徐々に増えてきています。
スタンダードな内容としては、実践と学習を組み合わせた研修スタイルで、アクションラーニング型研修と呼ばれています。これは、何人かのチームを編成、自社の事業や経営上の課題を分析し、それに対してどのように改善をしていくのか議論を行なった上で、最終的には役員や社長へ発表するという形式が多く取られます。また、外資系企業では、参加者に対して上司やメンターが1on1でコーチングを行ったり、外部のエクゼクティブコーチを雇い、この参加者へのフィードバックと内省の機会に多額の投資をしますが、日系企業においてはチームメンバー同士の360度評価を行うケースが多く見られます。
こうした次世代リーダーシップ研修は後継者育成(サクセションプランニング)の観点でも今後更に注目されていくと思われます。
③管理職研修
課長や部長職といったマネジメント層を対象とする研修がいわゆる管理職研修と呼ばれるものです。一般的には2〜3日間ほどの期間を設けて新しく登用された管理職が集められます。内容としては、管理職としての基礎知識のインプットや評価方法の注意点、コンプライアンスに関する研修などを行います。また、最近ではコーチングや1on1が注目を集めていることから、コーチングの実践やフィードバックを受ける研修なども行われるようになってきています。
④オンボーディング
近年中途採用者が増加していることを受けて、中途採用者向けのオンボーディングも促進されてきています。
オンボーディングとは、新しい従業員やメンバーが組織やチームに参加した際の導入・統合プロセスを指す言葉です。具体的には、新しいメンバーが組織の文化、価値、環境、および彼らの役割や責任を理解し、効果的に業務を開始できるようにするための一連の活動や取り組みを意味します。
人材開発に関する代表的な概念の中にも「組織再社会化」という概念があります。これは、前述した組織社会化の一種で、入社した人からいったん前職の組織の信念や態度を抜いて、新たな組織の信念や態度を定着させることを指します。
オンボーディングはまさにこの組織再社会化を目指して行われる取り組みの一つです。
(2)現場で行われる人材開発
上述したような人材開発は、実際の業務を行う現場から離れて行われるタイプの研修です。
今回説明する人材開発はいわゆるOJTと呼ばれる、現場で行われる人材開発です。
人材開発の概念の中に「経験学習」と呼ばれる概念がありますが、これは挑戦を含む経験を積み重ねることで、そこで起こった出来事を内省することを通して自分の能力やスキルを高めることができるという理論です。
この理論は、「具体的経験」「内省的観察」「抽象的概念化」「能動的実験」という4つのステップから構成される循環型サイクルで、無意識で行っていたことを意識的に行えることに移行する際に活用できます。
OJTでは、こうした現場での具体的な経験から内省的観察を行い、それを他の状況でも応用可能な知識やルーティンとして作り上げ、実践を繰り返すことによってその学習サイクルを回していくことによって成長を促していきます。
人材開発を行う際の注意点
ここまで人材開発の目的やメリット、具体的な手法などについて解説してきましたが、最も大切な注意点としては人事施策の整合性を図ることです。
人事施策の整合性を図るとは、企業の中にある人事施策が一貫しているものになっているかどうかということです。
人材開発の効果を最大限発揮するためには、人材開発だけの力に頼らず、様々な人事施策を組み合わせた上で組織の課題解決を行うことが重要です。例えば、採用と人材の育成を考えた時、どういったターゲットを採用するかと、入社後どのように育成していくかはセットとして考えられるべきで、採用のみ、育成のみと切り離して考えることは整合性が取れません。
同様に、人事の業務を見たときに、機能で見ると採用、労務、評価、福利厚生など独立して存在しているかのように見えるかもしれませんが、全ての人事施策は経営戦略に基づいて行われるものです。
つまり、経営戦略と紐付けされた人事施策があり、それが連携して初めてシナジーが生まれ、経営や現場へのプラスのインパクトが発揮できると言えます。
人材開発を考える際には、この点をポイントにおいて考察するようにしましょう。
まとめ
人材開発は、個人の能力やスキルの向上だけでなく、従業員に行動変容を促すことで企業業績にプラスの影響を与えます。変化の激しい現代のビジネス環境では、これまでの研修型やOJT型のトレーニングを超えた適切なプログラムの設計と選択が求められています。
組織としての成功を追求するうえで、持続的な人材開発の取り組みは欠かせない要素であることを理解し、実践することが重要です。
フォスターリンク株式会社では、人材マネジメント企業として、人材開発や研修もサポートしています。人材開発や研修でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
参考文献
・人材開発・組織開発コンサルティング/中原 敦