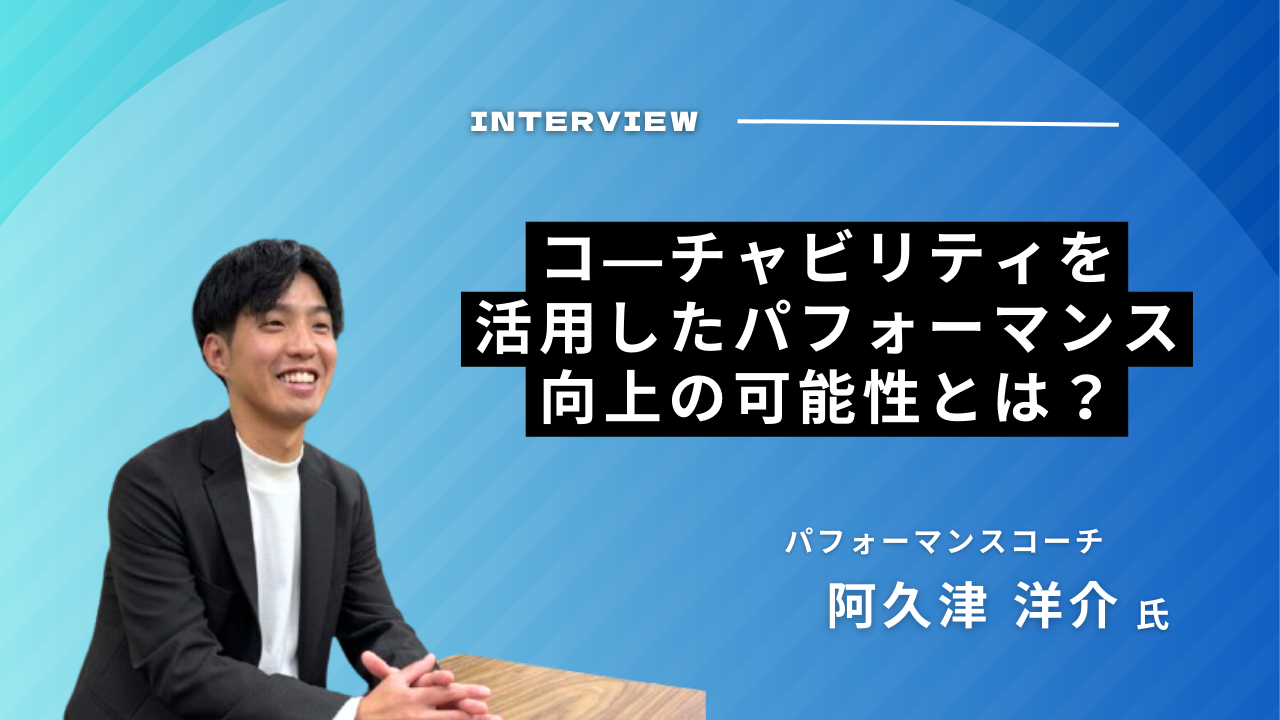「コーチャビリティ」とは、個人の成長とパフォーマンス向上を促進するために、建設的なフィードバックを求め、受け入れ、実行する意欲と能力とされています。
元々はスポーツの文脈において素晴らしいパフォーマンスを生み出すための基本的な資質のひとつとして、1960年代後半から1970年代前半の間に生まれて紹介された概念でした。
では、実際に「コーチャビリティ」を理解し取り入れることで、どのように個人の成長につながるのでしょうか。今回は、スポーツ選手を中心にパフォーマンスコーチをされている阿久津洋介トレーナーにインタビューを行いました。

パフォーマンスコーチの仕事とは?
――パフォーマンスコーチとは具体的にどのようなお仕事なのでしょうか
パフォーマンスコーチの役割は、スポーツ選手や一般のクライアントが最大のパフォーマンスを発揮できるようにサポートすることです。パフォーマンスコーチは、身体だけをみていくというよりはパフォーマンスから逆算をしたアプローチをしていくというのが特徴です。
例えば、サッカー選手がこのタイミングで早く走るためにどういうトレーニングをすべきか、キックをする時に毎回ボールが上の方に飛んでしまう場合に、身体の機能としてどういうことが原因かを紐解き、フィードバックすることで、選手自身が実感しているものに対して、身体の話、トレーニングの話をしていきます。
選手が、自分自身のパフォーマンスが目に見えてわかるというのを実感した時に、続ける意欲が上がり当たり前にできるようになることで継続率も各段に上がります。
――ご自身もサッカーをされていたと記事で拝見しました。選手としての立場とトレーナーとしての立場の違いはどういったところでしょうか
自分だけのことをすればいいという選手の立場と、人を動かさなければならないというコーチの立場の違いを感じています。
自分の主観に従うだけでなく、コーチの立場では選手本人が理解しやすい状況を作る必要があります。例えば、ボールを蹴る感覚や試合でどう動いたらいいのかなど、客観的なデータや映像を入れてあげることが求められます。
その上で、本人の主観とすり合わせてあげるということが重要です。
コーチャブルな選手を育てる:フィードバックの重要性
――選手によってコーチャブルではないという方はいるのでしょうか
プロスポーツ選手の中でも、日本代表レベルの選手はかなりコーチャブルであると言えます。
私が見てきた中では、一流の第一線で活躍しており5年以上やっている選手はかなりコーチャブルです。
――コーチャブルではない方に対してはどんなアプローチをされていますか
心がけているのは、フィードバックをするときに段階を踏むことです。
例えば、この動きができない理由は、できていないか、できたかの〇×からスタートします。
次に、3択で、例えばジャンプをしたときにできない理由が、足で蹴っているから、先に上だけあがってしまっているから、全体で押し切れてないからのどれなのか。最終的には記述式で今できてなかった理由を言っていく。こういった段階を踏みます。
さらにレベルが上がると、この動きができていなくて、ここまで何回何セットこういう刺激をいれたけどそれでもできなかったのでアドバイスをください、となってきます。
そこの段階をちゃんと踏ませることでコーチャブルな状況にしています。
プロトレーナーが考える信頼とコ―チャビリティ
――この人だったら大丈夫という信頼関係をどうやってつくっていくのでしょうか
その方にとって、本当にメリットがあるかどうかという点は気を付けています。
些細なことであっても、ラフすぎる回答ではなく、その時間軸の中でうまくできる回答をしていくことが信頼度を失わないという意味で大事だと考えています。
コスパは悪いとは思いますが、その点を気にしているからこそ信頼度を得られていると思っています。
――ご自身がアプローチすることでコーチャブルになったという具体例はありますか
仕事がすごく早くはならないかもしれませんが、仕事のプロセスが理解できて、そのプロジェクトで考え方を覚えて、別のプロジェクトで違う派生の仕方でできていくということはあります。
私からはできるだけ、話の中でヒントを与えていったり、どう思ったのかについて聞いていいくようにしています。
そうすることで、最初はクローズドクエスチョンだった方がオープンクエスチョンになり、最終的に、こう思ったのですがどう思いますかと聞いてくれるようになっていきます。

< プロフィール >
阿久津洋介(あくつ ようすけ)
株式会社ライフパフォーマンス LP BASEパフォーマンスコーチ、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
1989年、千葉県出身。国際武道大学大学院 武道・スポーツ研究科修了。その後、ライフパフォーマンス設立のタイミングで大塚氏から参画の要請を受け現職。
インタビュー後記
今回のインタビューは、選手が主体的に成長できるような環境こそが、コーチャビリティ向上に不可欠であることを示唆しています。
阿久津氏は、単に身体的なトレーニングだけでなく、選手のパフォーマンスから逆算し、個々の課題を解決するためのフィードバックを提供することで、選手が自ら成長を実感できる環境づくりを重要視しています。
特に印象的だったのは、フィードバックの段階的なアプローチです。最初は簡単な質問から始め、徐々に選手が自ら考え、表現できるよう促すことで、選手が主体的に課題解決に取り組めるようにサポートしているそうです。また、信頼関係の構築においては、選手にとって本当に意味のあるフィードバックを提供することが大切だと強調していました。
阿久津氏の経験談は、コーチングに携わる方だけでなく、組織における人材育成にも役立つ示唆に富んだものであると考えています。