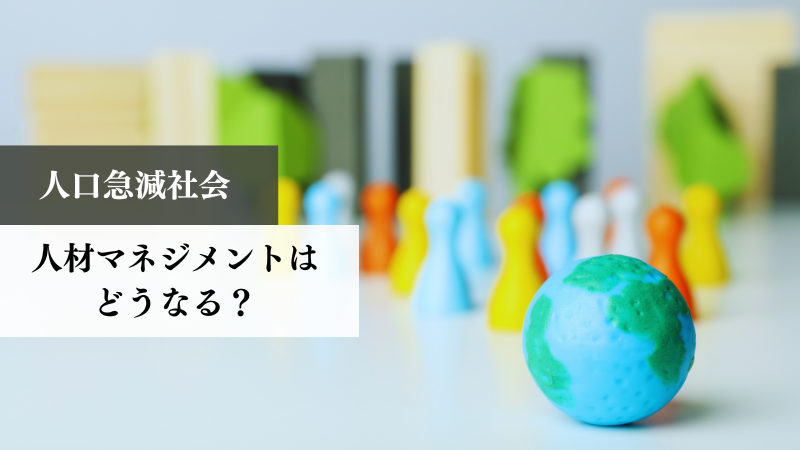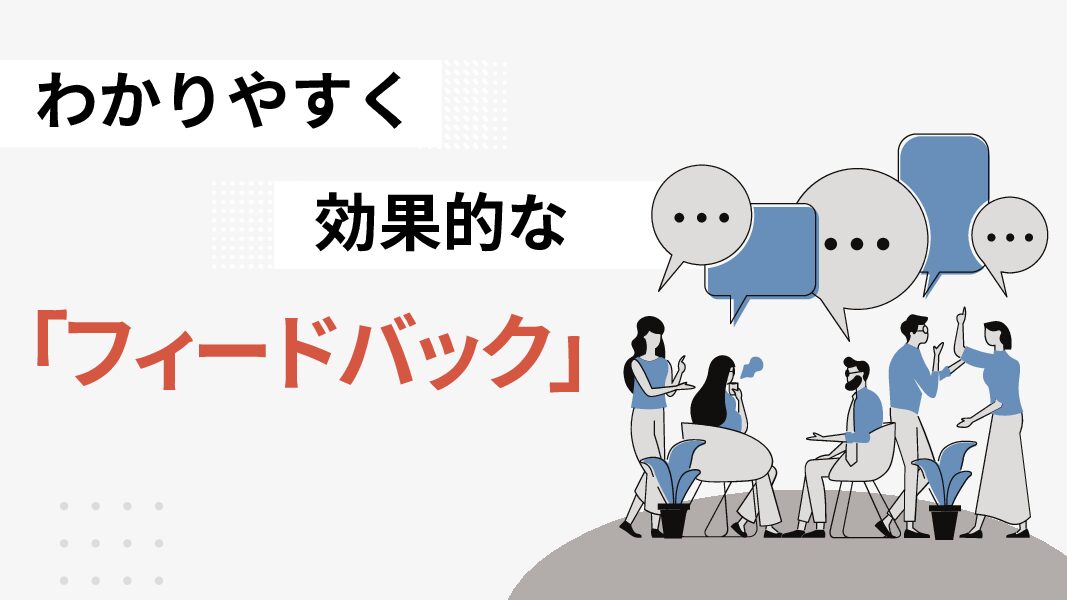国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口(令和5年推計)の出生中位・死亡中位推計よると、2070年時点の日本の総人口は現在の約7割の8700万人に減少、総人口に占める65歳以上人口の割合は38.7%(2020年でも28.6%)になります。2025年から2035年までの10年間を見ると生産年齢人口(15-64歳の人口)は7310万人から6721万人と約589万人減で、よく比較に出されている通り、毎年鳥取県の人口(令和2年国勢調査で55.3万人)以上の生産年齢人口が失われることになります。
より労働力の実態を反映している総務省の労働力調査年報(令和4年)では、労働力人口( = 就業者 + 就業する意志のある失業者)は2022年で6902万人でした。この数字は、働く女性やリタイヤを遅らせる高齢層の増加の影響によって、ここからの足元数年ですぐに歯止めのかからない減少局面を迎えるというわけではなさそうですが、いずれにしても総人口の減少に引っ張られる形になっていくでしょう。
生成AIを始めとした各種テクノロジーの伸展・活用によって従来と同じアウトプットを出すのに必要な労働力は減少するでしょうが、総タスクに占めるテクノロジーで解決できるタスクの割合の職種間の濃淡や、テクノロジー活用の巧拙により、労働力の需給は質的・量的にアンマッチな状態が拡大することが想定されます。
そうした人口急減・ウルトラ高齢社会*と言える環境を乗り越えていくために、企業・組織にはどういう人材マネジメントが求められそうなのか、既に多くのところで喧伝されている内容ではありますが、あらためてその方向性について試案をまとめました(* 国連の定義に沿った「つもり」の勝手な造語です。総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が28%以上の社会という意味で使用しています。国連では、7%以上の高齢化社会、14%以上の高齢化社会、21%以上の超高齢社会まで定義されています。)。あくまでも全体としての方向性の試案であり、各企業・組織においての個別解(何をどの程度取り入れどう全体としてのバランスを取っていくか)は別物であることはご留意ください。

【この記事の執筆者】
フォスターリンク株式会社 組織・人事コンサルタント 廣松 啓太
大学卒業後バイオベンチャーに入社し、健康食品の通販部門でフルフィルメント機能の立ち上げと整備に従事。同社IPO後、起業を経て、2015年フォスターリンク入社。コンサルタントとして中堅・中小企業を中心とした組織・人材マネジメントに関する課題解決に従事。
採用
人口急減で労働力の獲得・確保競争が激化すると、これまで企業が主に採用してきた層だけでは必要な労働力を確保出来なくなっていきますので、デモグラフィックダイバーシティ(性別・人種・年齢・障碍有無等、外見的な多様性のこと)が進みます。例えば、女性・シニア・障碍者・海外人材等々の採用が増えます。
厳密には採用ではありませんが、労働力の獲得という面で見ると、外部の労働力の活用(アウトソーシング)やテクノロジーの活用も進みます。外部労働力の活用と前述した採用層の多様化への対応では、これまでと異なる働き方への対応も求められます。例えば、リモートワーク・時短勤務・勤務地限定・ギグワーク等です。
顧客へ価値提供を行っていくための自社のオペレーションの、自社でやる部分と外部を活用する部分や、テクノロジーで担う部分と人間の労働力で担う部分等の再設計・再構築も進みそうです。経営陣等マネージャーは勿論のこと、人事の貢献も期待される分野だと思います。
採用の方向性に関連するキーワード
・DE&I推進
・働き方改革
・職務設計
配置
採用する従業員が多様化し、それに伴い働き方を多様化しようとすると、多くの企業・組織がこれまで前提として来たような企業・組織主導の配置転換は、少なくともこれまで通りの(企業・組織側から見た)自由度では出来なくなるということには自覚的である必要があります。
人材開発のところで後述するキャリア自律の文脈においても、配置転換の主導権は企業・組織側から従業員側に移行していく流れです。
そして、空いたポジションの充足のために従業員の自由な配置転換を前提出来ないので、ポジション充足のために採用が果たす役割が大きくなり、ここにこれまでの「採用→配置」から「配置→採用」への発想の転換が起こります。すなわち、採用してからどこに配置するのか考えるという順番ではなく、具体的な充足が必要なポジションから逆算して採用を行うという順番が基本(理想の人員配置を実現するための計画と実行のことを「要員計画」と言います。)になってくるでしょう。この場合の採用は、外部労働市場からの通常の採用もあれば、内部労働市場からの採用(すなわち、従業員との合意のもとでの配置転換。企業・組織側からの働きかけによる場合もあれば、自己申告制度・社内公募制度・社内FA制度等を利用した従業員側からの希望の場合もある。)もあります。
これもまた人事制度のところで後述しますが、企業・組織主導の自由な配置転換を前提できなくなると職能資格制度の大きなメリットのひとつがなくなります。また、要員計画や従業員側からの希望による配置転換の実現のためには当該業務の明確化が必要になることも合わせて、職能資格制度ではなく職務等級制度や役割等級制度の方が状況に適している場合が増えそうです(本来は職能資格制度においても業務の明確化は必要ではあるのですが、やっていない企業・組織の方が多いと思われます)。
配置の方向性に関連するキーワード
・配置転換の主導権は企業・組織側から従業員側へ
・要員計画(適時適所適スキルの人員配置)
・職務記述書/役割定義書
・自己申告制度・社内公募制度・社内FA制度
人材開発
ピラミッド型の年齢構成を前提とした終身雇用・年功序列型の雇用慣行・報酬体系は既に多くの企業で立ち行かなくなっており、それに伴って、従業員のキャリアの責任は企業・組織側が持つのではなく、従業員自身が「変化する環境において自らのキャリア構築と学習を主体的かつ継続的に取り組む」というキャリア自律という考え方が主流になっていきます。
この流れの中で人材開発の形も、これまでの企業・組織主導の全員一律に近しい形から、従業員個々人の主体的な学習を後押し・支援する形に変わっていきます。キャリア構築という意味でも、配置のところで前述しましたが、自己申告制度・社内公募制度・社内FA制度等を利用してもらって主体的なキャリア構築を後押ししてくことになります。
また、キャリア自律と合わせて多様な人材の多様な働き方が加わることで、従来とは異なった従業員同士の関わり合いの中で成果を作り出していくことが求められ、これまで以上に従業員個々人とチームとしての学びが重要になってきます。経験学習の考え方によると学びには内省的反省が必要であるため、それを促すフィードバックや、そのフィードバックをうまく受け取り活かしていくためにアンラーニングやコーチャビリティ、そうしたやり取りを良しとするフィードバック文化を醸成していくことがその成否の鍵を握りそうです。
最後に、キャリア自律を促進すると個人が特定の仕事や専門性にキャリア初期からコミットする傾向が強まって専門的なキャリア志向が一般的になり、複数の業務を統括するゼネラルマネージャーの育成が困難になります。従って、企業・組織の屋台骨を担っていく次世代リーダーシップ(究極的には次の社長)についてはこれまで以上に意識的に開発していくことが求められます。キャリアの初期から対象者を選抜し計画的に配置と人材開発を行うことが重要な一方で、敗者復活も取り入れた運用が肝要です。
人材開発の方向性に関連するキーワード
・キャリア自律
・フィードバック
・コーチャビリティ
・アンラーニング
・自己申告制度・社内公募制度・社内FA制度
・次世代リーダーシップの開発
人事制度(等級・評価・報酬)
配置のところで前述した通り、企業・組織主導の自由な配置転換を前提できなくなると職能資格制度の大きなメリットのひとつがなくなります。また、要員計画や従業員側からの希望による配置転換の実現のためには当該業務の明確化が必要になることも合わせて、職能資格制度ではなく職務等級制度や役割等級制度の方が状況に適している場合が増えそうです(本来は職能資格制度においても業務の明確化は必要ではあるのですが、やっていない企業・組織の方が多いと思われます)。
企業・組織の成長が停滞している中で、ピラミッド型の年齢構成を前提とした年功序列型の報酬体系が従業員の高齢化による総額人件費高止まりを引き起こし構造的機能不全を起こしている一方で、若年労働層は供給が減り獲得が困難になっていきますので、年功ではなく従事している職務や役職に応じて報酬が決まる体系が望ましくなります。これは、キャリア初期の低めの給料からキャリア後期に向けて高くなっていくという1社の中でのキャリア全体で貢献度と報酬のバランスを取る体系から、従業員が何歳であっても従事している職務や役職に期待される貢献度に対して定められた報酬を都度精算するようなイメージの体系になるということです。
人事制度の方向性に関連するキーワード
・職務等級制度、役割等級制度
代謝
代謝は、企業・組織から出ていくこと(=退出)を指します。
人口急減・ウルトラ高齢社会では、定年で引退してもらっている場合ではないです。従事している職務・役割に期待される成果を出せているのであれば、従業員本人が望めば雇用が継続されます。一方で、そうでないのであれば、何歳であっても定年とは関係なしに、他の活躍できるキャリアを探すことを促すのが基本線となります。ただし、定年制を廃止にするのか定年後に別契約に切り替えるのかや、退職勧奨や解雇については法制度も絡むため、具体的にどうなっていくかは未知数です。
転職自体を悪や裏切りとみなす見方はそぐわなくなります。
気持ちよく送り出し、次の転職先でのチャレンジがうまく行かなかった時や成長した後で戻って来てもらえるような、転職者同士や転職者と企業間のつながりを保っていくことが大事です。
代謝の方向性に関連するキーワード
・定年制廃止
・アルムナイ制度
人による働きかけ
これまで言及して来たのは全て仕組による働きかけを通じた人材マネジメントについてでした。
導入文にも書きましたが、これらの仕組はあくまでも全体としての方向性についての試案に過ぎず、各企業・組織においての個別解(何をどの程度取り入れどう全体としてのバランスを取っていくか)は、それぞれの置かれた事業環境・組織の目標と状況・組織の持つ変化の程度とスピードへの許容度と覚悟等を見極めながら探っていくことになります。
一方で、最後に、人による働きかけを通じた人材マネジメントにも触れておきます。
人による働きかけとは、個人間のコミュニケーションを通じた働きかけです。例えば、話をする、話を聞く、褒める、注意をするといったコミュニケーションを通じて働きかけを行います。仕組による働きかけと比較した場合、人による働きかけはその効果持続期間や効果波及範囲が限定的で、マネジメントの力量や個人間の相性によって効果の再現性にもムラがあるため、ある程度の人数を対象に働きかけを行っていかなければならない場合は、仕組による働きかけが効率的であると言えます。
しかし、やはり人があっと驚くような成果や成長を見せた時に、(当然本人の内的動機付けはあるとして、それに加えて)外部からの働きかけとして、仕組による働きかけと人による働きかけのどちらがその成果や成長に寄与していることが多そうか、または実体験として多かったかと問われれば、人による働きかけの方だと答える方が多いのではないでしょうか。
私自身もそう考えていますし、周囲の心を奮い立たせるというと少し大袈裟かもしれませんが、そうしたことは人にしか出来ない働きかけで、そして今後より一層重要度が増していくものなのではないかなと感じています。
人による働きかけの方向性に関連するキーワード
・周囲の心を奮い立たせる
まとめ
今回は、人口急減・ウルトラ高齢社会の人材マネジメントの方向性の試案をお届けいたしました。
経営陣・マネージャー・人事・従業員どの立場の方もそれぞれ難しい課題が目の前にあるのだなと本試案をまとめながらあらためて感じておりましたが、もしこれがこれから課題に挑戦する方々の何か役に立ったり、あるいは挑戦にご一緒させて頂く機会に繋がれば望外の喜びです。
ここであげた方向性やキーワードについて何かございましたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。