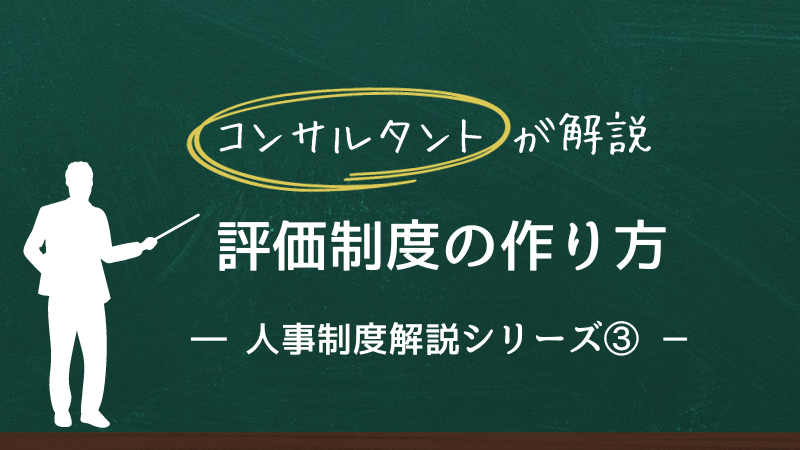人事制度の1つである評価制度は、等級制度やジョブディスクリプションによって明示された経営者が従業員に求める期待値に対する、従業員のある一定期間における実績値を測る仕組です。
等級制度・報酬制度と日々の現場のマネジメント行動と連動することで、経営者が従業員に求める期待値とそれに対する従業員の実績値に応じた処遇決定方法を通じて理想的な人材配置・組織の方針の浸透・動機付け・マネジメントの効率向上の実現を意図した仕組です。
近年、社会情勢や働き方の変化を受けて多くの企業が評価制度の変革を求めており、新しいアプローチや方法論も注目されています。
この記事では、主にそもそも評価制度とは何か、その効果と設計方法について解説します。
評価制度とは
評価制度とは、等級制度やジョブディスクリプションによって明示された経営者が従業員に求める期待値に対する、従業員のある一定期間における実績値を測る仕組です。
等級制度・報酬制度と並ぶ、人事制度の1つです。
評価制度が等級制度・報酬制度と大きく性格が異なるのが、その運用に現場が深く関与する必要があるという点です。評価制度の趣旨の理解や制度運用に対する現場のWill・Skillが十分でない場合、狙い通りに制度の運用が出来ず、人材マネジメント全体の成否に大きな影響を与えてしまいます。
評価制度は運用が9割です。制度そのものの設計だけでなく、運用開始前の準備や運用状況に応じた継続的な改善活動を行っていくことの方がより重要だと言えます。精緻な設計よりも、シンプルで運用しやすい設計の方が目的に適うでしょう。
「考課」との違いは
評価ではなく「考課」という言葉を用いている企業もあります。
「考課」とは、課題を考えるということを意味し、人事評価をいわゆる査定や処遇の格差付けだけを目的としたものではないことを意図した表現です。
現在は一般的には人事評価と表現されることが多いですが、後述する通り、評価制度には査定機能だけでない目的が含まれます。
評価制度の効果
評価制度の効果として主に挙げられるのが、処遇に対する根拠の明確化・人材開発・組織の方針の浸透・動機付け・マネジメントの効率向上の5点です。
評価制度も含む人事制度(等級制度・評価制度・報酬制度)の究極的な目標は組織目標を持続的に達成することであり、その代表的な中目的は①理想的な人材配置の実現、②組織の方針の浸透、③動機付け、④マネジメントの効率向上の4つであり、そのために経営者が従業員に求める期待値とそれに対する従業員の実績値に応じた処遇決定方法を通じて組織・人材マネジメントを行おうとするものだとこちらの記事で解説しました。
ここでは、評価制度の効果がどのように人事制度全体の狙いの中で機能しているのかを解説します。
処遇に対する根拠の明確化
まず1点目は従業員の処遇に対する根拠の明確化です。
上述した通り、そもそも人事制度(より正しくは、等級・評価・報酬制度を中心とした伝統的な所謂人事制度)は、処遇決定方法を通じて組織・人材マネジメントを行おうというアプローチをとっています。その中で評価制度は従業員の実績値を測ることで処遇決定の根拠を明確化します。それが主に報酬制度で定められた処遇決定メカニズムのインプットとして利用され、結果、処遇が最終決定されることになります。
人材開発
2点目は人材開発です。
上述した通り、人事制度の代表的な中目的に理想的な人材配置の実現があります。
理想的な人材配置というのは、現在の組織内の人材を上手く配置するという静的な配置だけではなく、採用・人材開発・代謝も含めた時間軸の上での動的な配置を意味します。その中で評価制度は、現在および将来求められる期待値を周知し、直近の実績値を測りそれを従業員にフィードバックすることを通じて人材開発の一端を担います。
組織の方針の浸透
3点目は組織の方針の浸透です。
上述した通り、人事制度の代表的な中目的に組織の方針の浸透があります。
評価制度は期待値の周知+実績値へのフィードバック+処遇の連動を通じて、組織の価値観や戦略に基づいた望ましい思考・行動様式を従業員に繰り返し伝え、浸透させる機能を担っています。
期待値の周知は評価項目や評価基準として明示され従業員に周知されます。
実績値のフィードバックは代表的には中間面談や評価面談を通じて行われます。
処遇の連動については評価制度だけによる効果ではなく報酬制度と合わせての効果になりますが、評価基準に沿った望ましい思考・行動様式をし成果をあげた人が報われるというメッセージを示すことで、方針に従う行動をとるインセンティブを高めます。
動機付け
4点目は動機付けです。
上述した通り、人事制度の代表的な中目的に動機付けがあります。
評価制度では主に目標設定と達成感や承認の提供により動機付けを行います。
一方で、評価制度による動機付けは近年では疑問視される部分も多く、特に外発的動機付けのみに過度に依存している点には批判があります。
マネジメントの効率向上
最後はマネジメントの効率向上です。
評価制度が組織内のマネジメントの共通基盤となることで、マネージャーは個別に評価項目・評価基準・評価方法を考える必要がなくなり、組織内で統一された手法で日々のマネジメント活動を行うことが出来るようになります。
評価制度の種類
評価制度は、被評価者のどういった点をどう評価するのかによって様々な種類に分類されます。
大枠で言うと、評価の対象としては、仕事を遂行する上でのインプット・プロセス・アウトプットに分類されます。
この場合のインプットとは、被評価者の持つ知識や保有能力を、プロセスとは被評価者の示す態度や取り組み姿勢、行動が該当します。そしてアウトプットは、財務的・非財務的な成果ということになります。なお、この場合の非財務的な成果とは、利益目標につながるような顧客満足度や業務革新のレベルなどを指します。
等級制度に関する記事の中で説明した、「役割等級制度」に基づく考え方の下では、仕事のアウトプットを基準に会社の期待値を示し、その実績値を成果として把握するため、評価の対象としてはアウトプットとそこに関連するプロセスが中心となります。
一方で、「職能等級制度」に基づくと、インプットやプロセスでの評価も主軸となっていくことが考えられます。
なお、このアウトプット部分の財務的・非財務的成果については、企業によって名称は様々ですが、成果評価や業績評価などと呼ばれ、プロセス部分については行動評価や情意評価、インプット部分については能力評価やスキル評価などと呼ばれています。
人事評価制度の変遷
人事評価制度はこれまで何度か大きな変遷を遂げています。
この変遷を学ぶことで、今後の自社の評価制度をどのように設計していくべきか考察する視点が加わるでしょう。
人材マネジメントの世界ではこれまで大きく、年功主義から能力主義、そして成果主義へと移り変わっています。
近年では、さらに職務主義という考え方も注目を集めてきています。最新のトレンドについては後述しますので、ここではこれまでの変遷と近年の変化について解説します。
年功主義とは、年齢や勤続年数を処遇決定の際の判断軸とする考え方です。新卒一括大量採用を行い、同じタイミングでほとんどの社員が昇格していく年功主義のモデルも、経済が右肩上がりに成長していた時代では通用していました。
その後、オイルショックを契機とした経済の鈍化、高齢化の進展などを背景としてポスト不足が顕在化してくると、年功主義から能力主義への変換が図られていくことになります。
能力主義とは、いわゆる職能資格制度を中核とした人材マネジメントの手法で、職務遂行能力の有無によって処遇の格差を設けるという考え方のもとに設計されています。
当時は年功主義を脱却するための制度として普及しましたが、職務遂行能力は年々身についていくものであり、時間経過と共に消滅するものではないため、結局は年功主義的な運用となってしまうというデメリットが生じました。
そしてプラザ合意の円高不況、バブル崩壊の中で注目されてきたのが、成果主義です。
これは、業績や成果に基づいて処遇を決定する考え方です。成果主義は新しい概念というよりも、もともと年功主義下においても、能力主義下においても存在していた概念ですが、重視されるウェートが大きくなってきたと表現する方が適切かもしれません。成果主義はバブル崩壊後の人材マネジメントを刷新するための考え方として多くの企業が採用しましたが、次第に弊害が指摘されるようになりました。
それは、「成果」が結果を強く連想させることから、結果を出さなければ意味がないというメッセージとして強調されていったことが起因しています。具体的には職場内の人間関係にも問題を引き起こしたり、人材育成の風土が醸成しずらいといった問題が出てきました。
そうした背景や、テレワークの進展により従業員の業務を見える化したいというニーズの高まりもあり、近年では職務主義という考え方が注目されてきています。これは、いわゆるジョブ型と呼ばれる考え方で、人の能力や成果ではなくジョブ(職務)の価値に応じて処遇を決定する仕組みです。
欧米では古くから普及している考え方ですが、日本でも大手企業を中心としてジョブ型への転換を図る企業も増えてきています。
人事評価制度の設計方法
人事評価制度設計の際のステップとしては、以下の7つのステップが挙げられます。
それぞれのステップごとに詳しく解説していきます。
この場合のコアプロセスとは、業績を向上させていくための仕事の進め方を指します。
このコアプロセスはその会社ごとの事業戦略やビジョンに裏付けされています。既存事業以外にも、新規事業を進める際にも、事業戦略上必要と思われる仕事の進め方もコアプロセスとなります。
上述したように評価制度を組織のマネジメント手段の一つと考え、組織内で人が人をマネジメントする目的に立ち返って考察すると、その目的は業績を向上させることと考えられます。
つまり、事業戦略やビジョンに裏付けされたコアプロセスをもとに人事評価制度を設計し運用していくことによって、コアプロセスを強化し、結果的に事業戦略やビジョンを組織内に浸透させていくことにつながるということが言えます。
そのため、実際に人事評価制度を設計する前段階で事業戦略やビジョンを確認し、コアプロセスを明確化するというステップが重要となります。
人事評価要素とは、その人事評価制度において評価の対象となる項目を指します。
評価項目としては大別すると下記の3つが挙げられます。
①インプット
②プロセス
③アウトプット
コアプロセスを明確にすると、その過程の中で組織にとって重要な評価要素が見えてきます。こうした評価要素のうち、何を実際に評価の対象にするべきかを整理していくのがこのステップで行うことです。例えば、営業成績(アウトプット)が抜群であれば協調性や信頼性など(プロセス)が著しく劣っていた場合でも評価することにするのかどうか。こうしたことも考慮に入れてコアプロセスを意識しながら検討を行い、必要な評価要素に対して多面的に設計していくことが求められます。
人事評価基準の設計には、(1)評価等級基準(2)評価尺度基準の2つの設計が必要です。
(1)評価等級基準の設計とは、STEP2.で設計した評価要素ごとに等級単位別の評価基準を作っていくことを指します。例えば、企画職に4つの等級があり、評価要素がA~Dの4つあったとすると、評価要素Aの1等級の評価基準、評価要素Aの2等級の評価基準といったように、合計16個の評価基準を作っていくことになります。
評価等級基準の設計が完了したら、次に(2)評価尺度基準の設計に移ります。
評価尺度基準とは、人事評価で実際に用いる「S」「A」「B」「C」「D」などの標語や、「5」「4」「3」「2」「1」などの評価点を決める際のものさしのことを指します。(1)評価等級基準の設定だけでは、判断基準となるだけでどの程度その基準を満たしているかについてはジャッジができません。そのため、そのレベル感の濃淡を判別していくために(2)評価尺度基準の設計が必要となります。
(2)評価尺度基準には、大別すると絶対評価と相対評価の2つがあります。
絶対評価とは、他の人の評価とは切り離してその被評価者自身の評価をそれぞれの評価基準と照合して評価する考え方です。一方で相対評価とは、同じ組織やチームメンバーを順位別に一定の評価レベルに割り当てる考え方です。
絶対評価のみ、相対評価のみ、またはその組み合わせのどれを利用するかの考え方については、どれが正解というものではないため、組織の文化や戦略の方向性なども総合的に考慮した上で判断する必要があります。
組織で定められた、等級や役割、職種ごとに求められる役割や与えられた権限、能力の大きさ、成果の大きさなどをもとにして、評価項目の組み合わせを設計していきます。
これは、等級と評価項目が共通の場合もあれば、違う組み合わせとなる場合もあります。自社の人事制度の方向性を検討した上で設計していきましょう。
評価者体系とは、誰が誰について評価するかを決めて体系化したものを指します。例えば、1次評価者、2次評価者、最終評価者(機関)を被評価者別に決定した表がイメージしやすいでしょう。
通常はライン組織上に沿って被評価者と評価者を決めていく形になりますが、最近では「360度評価」を取り入れる企業も増えてきています。360度評価とは、上司からの一方的な評価ではなく部下が上司を評価したり、同僚同士で評価しあう仕組みを指します。部下や同僚が評価を行うとなると、こうした流れも予め評価者体系に組み込んで設計していく必要があります。
人事評価期間とは、被評価者を評価する際の対象となる期間です。
評価制度の目的を踏まえると、一定の期間を設けて評価をする必要が生じます。通常は半年や1年間を人事評価期間としている企業が多いですが、最近ではこの評価期間のスパンが短縮されていく流れも出てきています。
なお、1年間という枠組の中では判断が難しい職種もあります。例えば、研究開発職や技術開発職など結果が出るまで数年、中には数十年以上かかるという職種です。
こうしたケースでは、人事評価を定期的に行いながらも、報奨制度や奨励制度を設けるなどしてモチベーションを維持していける人事施策を並行していく必要も出てくるでしょう。
STEP6.までが完了したら、それを人事評価表としてまとめ完成させていきます。
人事評価表には様々なタイプがありますが、そのタイプを決める要素としては以下の3点が影響します。
①個人単位で作成するか、組織単位で作成するか
②評価基準、評価要素群や着眼点明記の有無
③自己評価欄の有無
①については個人単位で作成している企業が一般的ですが、中には組織やチームなどのメンバーを一覧形式で評価し、評価結果を記入するタイプの評価表もあります。
また、②具体的な評価要素や評価要素を群として分けた評価要素群、判断のウェートや着眼点を記載しているかどうかでも大きくタイプは異なります。
③自己評価欄の有無については、自己評価を被評価者にしてもらうことによって評価者が心理的に評価をしやすくなり、被評価者にとっては自らを振り返る機会にもなるというメリットがあります。ただし、記入によって被評価者へのプレッシャーを高め、負担を生じさせたり、被評価者が記載した内容に評価者がつられてしまうというデメリットがあるため、運用も含めて検討する必要があります。
繰り返しになりますが、評価制度には処遇の格差付けを行う査定機能があります。
例えば、同じ職層の従業員に対して、「賞与」という処遇に対しては成果評価と行動評価のみを評価し、「昇給」と「昇降格」という処遇に対しては、成果評価、行動評価、能力評価を対象としていくといったような検討です。より具体的に言えば、「賞与」に対しては成果評価が30%、行動評価が70%というように評価要素群によって評価のウェートを設けて設計していくことが一般的です。
人事評価制度構築・運用の際の注意点
評価制度がうまく機能することによって、会社にとっては戦略実現のために従業員に対してふさわしい行動や成長を促すという仕組みを作ることができます。また、それを定期的に適切に回していくことによって盤石な人事評価の相互作用のサイクルが形成されていくことになります。
よって、ここでは評価制度全体における大原則と人事評価の場面において特に陥りやすい傾向に分けて詳しくご説明します。
評価制度の人材マネジメント上の目的を実現するためには、被評価者が納得のいく評価制度となっていることが求められます。この納得感を醸成するためには以下の5つの重要な原則があります。
(2)評価基準の明示
(3)評価基準への理解
(4)評価基準の遵守
(5)評価責任の自覚
(1)公正な評価を行うためには、恣意的な悪意による評価を生じさせないようにすることが重要です。評価者の面談任せにせず、定期的に人事部門も被評価者と面談を行うなどして評価関係にある社員達に問題が起きていないかチェックをしていくことが必要です。また、合わせてなされている評価が推測や思い込みなどによる判断ではなく、事実に基づいた評価となっているかどうかもチェックしていきましょう。
(2)から(4)は、相互に関連する原則となっています。評価基準を事前に明示することが、評価への納得感を醸成するための重要な要素となり、それを被評価者が理解し、評価者が評価基準を守ることによって人事評価の目的を実現できるようになります。
これは相互に関連性はあるものの、一つ一つが重要な原則であり、どれか一つが欠けても機能しないという意識が大切です。
(5)評価を行う者は、評価の良し悪しに関わらず、被評価者の成長に責任を負っているという自覚を持つ必要があります。人事評価は被評価者のキャリアや生活に大きな影響を与え、評価責任を自覚しない評価者からの評価はモチベーションを低下させる要因の一つとなることも自覚した上で評価を行うことが不可欠です。
基本的に上述した5原則が守られていれば適切に人事評価が行われていくこととなりますが、人事評価の際に評価者が陥りやすい特長的な傾向があります。評価の際には、こうしたエラーが生じていないか注意しながら評価を行うようにしましょう。
(1)ハロー効果
一つの事実により全ての項目が良いと判断したり、全て悪いと判断したりしてしまうことを指します。
ハロー効果を克服するために、一つの事実にこだわらずにできるだけ多くの事実を持って判断していく必要があります。
(2)寛大化・厳格化傾向
高い評価結果や低い評価に集中する傾向を指します。
こうした傾向に対しては、「S」「A」などの評価尺度基準について具体的に考えながら評価をしていくことが効果的です。
(3)中心化傾向
無難な中央値付近の評価に集中してしまう傾向を指します。
評価に対する自信がない評価者が陥りやすいエラーと言われています。こうした傾向に対しても評価尺度基準についてよく念頭において評価をしていくことが効果的です。
(4)論理的誤差
頑張っているのだから能力も高いはずだと、推論で評価判断を下してしまうエラーを指します。
これに対しては、能力のレベルについては行動事実を持って評価するなど事実に基づいた判断を下すことが必要です。
(5)対比誤差
評価基準に基づいて評価を行うではなく、過去の自分との比較で評価を行ってしまうエラーを指します。このエラーを防ぐためには、評価基準をしっかりと理解してのぞむことが重要です。
人事評価制度の最新トレンド
社会情勢や働き方の変化によって、評価制度にも多種多様なトレンドが生まれています。ここでは、そのトレンドの特徴と具体的な手法についてご説明します。
①フィードバック期間の短縮
②多面的な評価
③行動や行動特性を基にした評価
④評価尺度基準を用いない
①の特徴が表れている評価制度としては、リアルタイムフィードバックやノーレイティングが挙げられます。
これは、半年や1年という単位では評価がしずらいという企業が導入し始めている制度で、2週間や1ヶ月などの高頻度でミーティングの場を設け評価の振り返りやフィードバックを行います。
こうした制度を取り入れることで、上司と部下のコミュニケーションが活発になり、その時々の職務の変化に応じた目標設定がしやすいというメリットがある一方で、目標設定と評価の負荷がかかりやすいというデメリットもあります。
②の特徴を有する代表的な評価制度は、360度評価が挙げられます。また最近では、ビアボーナスといった従業員同士で評価を行い、報酬を送り合う制度なども登場しています。社内のコミュニケーションを活性化させたり、従業員の新たな面の発見に役立つ制度ですが、導入コストがかかったり、馴れ合いにならないように明確な基準を作る必要が生じます。
③は、バリュー評価やコンピテンシー評価と呼ばれる評価制度に特徴が表れています。
バリュー評価は目標達成だけでなく、一歩踏み込んだ行動力を評価するもので、コンピテンシー評価は優れた業績を出している人に共通している行動特性を基にした評価制度です。人材育成の観点でもメリットがありますが、定性的評価とならないようリサーチをしたり評価基準を明確化する必要は生じます。
④はノーレイティングに代表される特徴です。
ノーレイティングとは、従業員を「S」「A」など評価尺度基準で判断をせず、リアルタイムに目標設定とフィードバックを行い、その都度従業員を評価していく制度です。繰り返して行うことにより、上司と部下の信頼関係を醸成しやすいというメリットがある一方で、上司への負荷がかかりやすいため、業務の時間配分を設計していく必要があります。
まとめ
評価制度は、企業の戦略と連動しながら処遇の根拠を明確にし、従業員のパフォーマンスを最大化していくための仕組みです。近年のトレンドでは、短期間でのフィードバック、多面的な評価、ランク付けの廃止などよりダイナミックなアプローチが注目されています。
現代の競争環境で成功を収めるためには、組織として従業員に求める要素を正確に評価し、その成果を最大化するための戦略を練り続けることが求められると言えるでしょう。
フォスターリンク株式会社では、人材マネジメント企業としての実績とノウハウを活かし、評価制度を含めた人事制度に関するコンサルティングを行っています。評価制度、人事制度の設計や運用などにお困りの方は、まずはお気軽にご連絡ください。